19世紀の音楽界
19世紀のロシアの音楽―前編―
前のページで見た、ナポレオン戦争から世紀末にいたるまでの100年近い間に、ロシアの音楽界もだいたい同じようなことが起きていました。ちなみに、ナポレオン戦争頃にドイツで活躍していたのがベートーヴェンというのを大体の目安にしてください。

戦争の頃が、ちょうど脂が乗り始めた時期です
ちなみに、この人たちは大体以下の感じです。
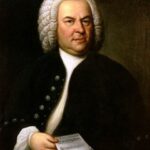
もう亡くなってから半世紀以上になります。
そろそろ思い出されてブームになるころです

亡くなってからまだ15年前後です

亡くなってからまだ10年経ってません
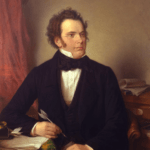
最近注目の若手です。
まあ、若死にしてしまうのですが……

ちなみに、この頃私はまだ存命です
このくらいの時期、ようやくロシアでは自分の国の作曲家が曲を作り始めるころでした。グリンカやダルゴムイシスキーあたりがそれにあたります。なお、このグリンカですらシューベルトより年下なので、かなり若い存在です。
これ以前、18世紀のいわゆる「女帝の時代」は、フランス人やイタリア人作曲家の方が有力でした。例えば、エカチェリーナ2世は宮廷音楽家に以下のイタリア人を招いています。

技術者はドイツ人が素晴らしいが、
文化はやはりイタリアから輸入しよう
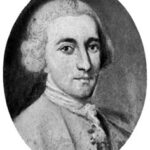
オペラ・ブッファの大家としておなじみのガルッピです

フランス流の奏法をイタリアに持ちこんだトラエッタです

ロッシーニ以前の大家だったパイジエッロです

ロッシーニ以前の大家だったチマローザです
一方ロシア帝国からは留学生も派遣されえており、その中でもとりわけ目立っていたのが、ベレゾフスキーやボルトニャンスキーなど西側からの窓口としてその影響も強かった、現在のウクライナにあたる地域の出身者でした。

イタリアで学んだあと、ロシア帝国では初めて鍵盤作品・交響曲・室内楽作品を作りました。
もっとも早死にしてしまうのですが……

イタリア留学中にオペラを作りました。
その後多数の楽曲を作り、帝室合唱隊監督の任につきました。
なので、言ってしまえば、18世紀のロシア音楽界とは、イタリア人やウクライナ出身者が大部分を占めていたとも書けます。
それが、若干変わるのが、次の皇帝のせいです。

母・エカチェリーナ2世の外国びいきなど葬り去ってしまえ
この人は、一瞬で暗殺され、次の代にはまた元に戻ります。

父上のような真似をすると殺されるのだ。
いったん、祖母の代のやり方に戻そうと思う
しかし、この一瞬の外国文化排除の結果、ロシア貴族に自国文化への関心がもたらされました。また、このパーヴェル1世の縁故を便り、クレメンティが西からやってきました。かつて皇太子だった頃に母親に送られたオーストリアのヨーゼフ2世の宮廷で会っていたためです。

遠路はるばるようこそ皇太子殿下
これが、今うちの宮廷にいるクレメンティだよ

あの、モーツァルトとも対決したとかいう……

もっともその話は真偽不明なのですが……
彼がたどり着いた時にはパーヴェル1世はすでに暗殺されていたのですが、クレメンティは弟子のフィールドに店頭で演奏させて、最新鋭の「イギリス式アクション」のピアノを売りさばきます。

え?パーヴェル1世がもういない?
こうなったらこのままピアノ屋でもやって稼ぐか……

今演奏しているこのピアノフォルテ。
ピアノフォルテという名前の通り、クラヴィコードやチェンバロと違って強弱がくっきりとつけられるんですよ
また、フィールドは教育者としてもすぐれていたので、瞬く間にロシアにピアノ演奏の伝統を根付かせます。

以下が私の弟子です

後世、ロシア史上最初の作曲家として祀られてしまったグリンカです

バラキレフやズヴェーレフ、ヴィロインクの師匠にあたるデュビュックです

他には私の師匠のアントン・ゲルケなんかもそうですね
このように、ナポレオン戦争が終わった後もこれまでと同様、西から音楽家を招き、その人たちが音楽を広めるという点はあまり変わりませんでした。ただし、その招く地域が次第にドイツやオーストリアになっていきます。先ほど挙げたクレメンティ、フィールドのほかにはシュポーアなども代表例です。

大半の人はファッションか何かで聴いてるだけだけど、
熱心な人もいるにはいるなあ
例えば、アレクサンドル1世の皇太子時代のピアノの先生は、バッハの孫弟子のヘスラーでした。

そもそもウチの家系は代々音楽好きで名が知られていますからね

ロシアに当時そこまで知名度があるとは言えないバッハを広めたのは、
実質的に、孫弟子にあたる私かもしれません
というか、この頃の音楽事業は基本的に皇帝が主導です。皇帝はペテルブルクやモスクワで、例えばマリインスキー劇場だったりボリショイ劇場だったりといった、自前のオペラハウスでオペラを開かせます。それに、貴族が音楽家として加わり、皇帝や貴族の農奴たちが演者などとして関わっていったのです。
一方、19世紀前半というのは、ヴィルトゥオーソの時代です。簡単に言うと、凄腕ピアニストやヴァイオリニストが名をはせ、パリなどの栄えた土地をめぐって身を立てる時代です。
パガニーニ、ショパン、リストなどはこれで国際的な名声を得ます。なお、彼らの一部はロシアのペテルブルクの宮廷にも訪れており、例えばリストは1843年にやってきてロシアにバッハブームをもたらすことになりました。
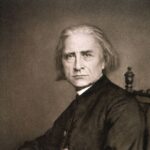
若干忘れられがちですが、私はオルガン奏者でもあるのですよ
一方で、ロシア領からも同様の存在が現れました。アントン・ルビンシテインです。
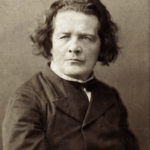
とはいえ、今のモルドバ出身なんだけどね
アントン・ルビンシテインは、ロシアに戻ると、リベラルな考えの持ち主だったミハイル大公妃エレーナのサロンに迎えられます。これが1852年です。

やはり、少しずつでも社会を良くしなければ……
ここで意気投合した2人は、1859年にペテルブルクにロシア音楽協会を築きます。アントン・ルビンシテインは弟のニコライ・ルビンシテインをモスクワに派遣するなど、ロシア各地で同様の組織を作らせました。
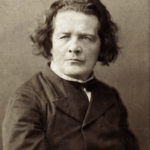
弟も才能があるし、
モスクワを任せられるだろう

わかったよ兄さん
ロシア音楽協会は、さらに1860年からエレーナのおひざ元で教育活動を始めました。これが1862年にペテルブルク音楽院になり、アントン・ルビンシテインが院長になります。このペテルブルク音楽院には、例えば西側からピアニストのレシェティツキが招かれるなど、西側の音楽を根付かせる拠点として運営されました。

リストの兄弟弟子です
1866年にはニコライ・ルビンシテインもモスクワで、ニコライ・ペトロヴィッチ・トルベツコイやユルゲンソンの協力の下にモスクワ音楽院を作りました。

ちなみに哲学者のエフゲニー・トルベツコイ、セルゲイ・トルベツコイは、
私の息子です
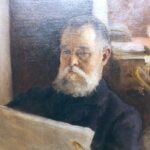
私はその後、いわゆる老舗の楽譜出版社となります
しかし、こういう人たちも出てきます。あんなの西の真似をしたエリート養成コースでしかないのではないかと。

あんなの、エリート向けのアカデミーコースじゃないか
この、今でいうストリート系的な人たちが、おおよそ以下の人たちです。
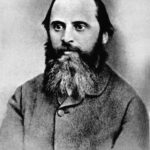
バラキレフ!

キュイ!

ムソルグスキー!
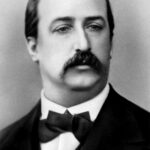
ボロディン!

リムスキー゠コルサコフ!

(5人そろえて)力強い一団!
いわゆる「ロシア5人組」です。
この人たちはバラキレフ以外はアマチュアで、簡単に言うと「西の真似なんかしてるアカデミーの連中と違って、俺たちは俺たちらしい音楽でロシアの音楽を発展させる」的な人たちです。スターソフのプロモーションのせいで実態はよくわからなくなっていますが。
それはそれとして、ペテルブルク音楽院ではこの人が見つけだされました。チャイコフスキーです。アントン・ルビンシテインは彼を弟・ニコライ・ルビンシテインの下におくります。

これからはモスクワの発展に力を入れます

ありがとう!
助かるよ!
ちなみに、このチャイコフスキーもいわゆる雑階級人でした。確かに音楽院はバラキレフたちの言う通り、前代以来の貴族階級のトレーニング施設ではあったのですが、貴族以外もようやく頭角を現し始めたのです。
しかし、音楽性としては、チャイコフスキーはルビンシテイン兄弟の影響下の、いかにもな西側風のものです。当然、5人組とルビンシテイン兄弟+チャイコフスキーあたりの勢力は対立します。
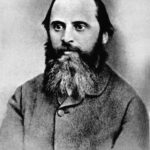
でも、民衆にも音楽が必要でしょう?

理想は経験的にもわかるんだけどねえ……
ここで、アントン・ルビンシテインはバラキレフに一度ロシア音楽協会の指揮者を任せてみました。
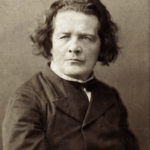
一度普通の音楽家に戻る。
そんなに言うなら一回任せてやる
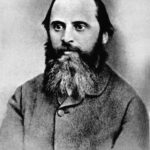
ほう
ところが、バラキレフはエレーナと対立し、あっさり退任しました。

やはりあの人とは合いません
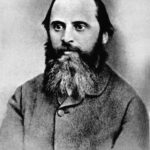
むぅ……
ただし、ナプラブニクなどがロシア音楽協会で5人組の曲を取り上げていきます。さらに、1871年には、リムスキー゠コルサコフがペテルブルク音楽院に招かれ、音楽院vs5人組という対立構造が崩壊していきます。
こうして、次第にアカデミー系vsストリート系というよりは、5人組とチャイコフスキー的な音楽の対立をある程度継承し、両音楽院で育っていく、ペテルブルク派(5人組系)vsモスクワ派(チャイコフスキー系)という軸になっていきます。
この世代が、1880年代ごろから活躍する、リャードフ、タネーエフ、リャプノフ、アレンスキー、ブルーメンフェルト、グラズノフあたりです。

1855年生まれで、
ペテルブルク音楽院で教わって以来ずっと5人組と親しくしています。
というか、ガチガチのペテルブルク派の重鎮ですな

1856年生まれで、
モスクワ音楽院で大金メダルを手に入れた、ラフマニノフの先例です。
1885年~1889年には音楽院の院長も務めたモスクワ派の重鎮です
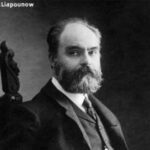
1859年生まれで、
モスクワ音楽院を出た後はずっとペテルブルク派と一緒に仕事をしていました。
ただ、一部では超絶技巧練習曲を補った人としか言われませんが……

1861年生まれで、
ペテルブルク音楽院を出た後、モスクワ音楽院の教授になってヒンシュクを買いました。
まあ、両派が和解し始めたのが私のおかげという声もありますが……

1863年生まれで、
ペテルブルク音楽院で育ちました。
長らく活躍していたのですが、今はホロヴィッツの師匠としか触れられません

1865年生まれで、
ほぼ5人組の個人的なレッスンのみで音楽家になりました。
先輩のリャードフと一緒にペテルブルク派の重鎮です
19世紀のロシアの音楽―後編―
この一方で、音楽史全体に大きく影響するので、ドイツに話を戻します。この人の登場です。
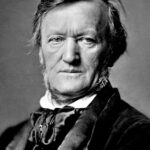
音楽は音楽にとどまらない、総合芸術であるべきなのだ!
音楽というのは、世界を革命する力にもなりえるのである!
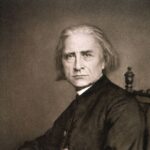
たびたび援助してきたけど、
なかなか面白いことをやりそうだ
ワーグナーが表現した音楽は、簡単に言えばそれまでにない新しい音楽でした。しかし、これに思いっきり着火してしまう出来事が起きます。

作曲に専念したいし、批評はもうやめにしよう。
編集はブレンデルくんに任せるよ

ワーグナーこそベートーヴェンの真の後継者!
ベルリオーズ、リスト、ワーグナーのような音楽こそ至高の芸術!

え?
手短に言うと、シューマンという作曲家がいました(SSRくらいの作曲家なので詳細は省きます)。彼は音楽批評を確立し、名声を得ていました。そのシューマンが、作曲に専念するために、ブレンデルという人に後を託しました。ところがブレンデルは、リストやワーグナーのような音楽ばかり取り上げてしまうのです。
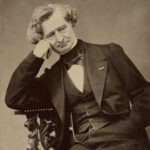
幻想交響曲とか作ったけど、
フランスにいる私の名前を勝手に使うのはどうなの?
さらに、シューマンの死後、この雑誌の創刊25周年の席に、シューマンの身近な人が全く呼ばれませんでした。これがさらに炎上させます。シューマンの未亡人のクララ、シューマンの弟子ブラームスらが、リストやワーグナーのような音楽への批判投稿を行ったのです

リストやワーグナーのような音楽を、
みんなが認めているわけがないから!
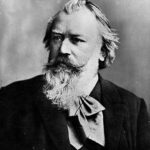
お力になりますよ
この中で、1865年、ワーグナーは楽劇「トリスタンとイゾルデ」をぶちあげました。この曲では、序曲でこれまでにない響き「トリスタン和音」をしょっぱなからぶちこみ(動画の10秒あたり)、以後クラシック音楽は徐々に既存のシステムから離れていく歴史になります。
が、当然これにキレる人もいます。
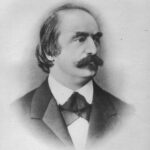
音楽ってのは音楽だけで成立するものなの!
ワーグナーなんてイロモノじゃなくて、ベートーヴェン、メンデルスゾーン、シューマンを引き継ぐのは、ブラームスみたいなやつなの!
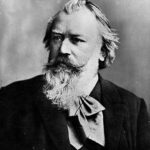
え?
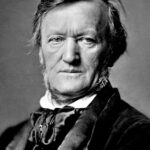
なんかヒートアップしてきたな……
無茶苦茶単純化して書きましたが、これが19世紀後半のドイツに起きた、ワーグナー派とブラームス派の対立です。とても簡単に言ってしまうと、ベートーヴェンの後継者は、エンタメなのか、抽象的な芸術なのか、どっちがふさわしいの?という戦いです。
それで、この流れで担ぎ出されたのが、この人です。

もう年老いたおじさんだけど、ワーグナーさんみたいな作曲家になりたいなあ。
でも、こんな地味な交響曲しか作れないや
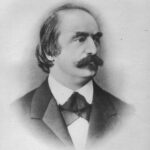
何!?ワーグナー派!?
じゃあ、敵だな!?
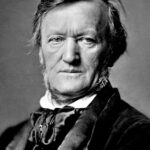
おお、もしかしたら、ベートーヴェンの後継者っぽい感じの曲の、
ブラームスのアレと戦える逸材かもしれない

え?
嘘です。無茶苦茶適当書きました。でもだいたいこんな感じで、ブラームスっぽい音楽しか作らないのにワーグナー派として持ち上げられる交響曲作曲家、ブルックナーが誕生します。
ただ、ワーグナーやリストは1880年代には亡くなってしまいます。以後、ワーグナーの正統な後継者判定は、リストの娘でワーグナーの下に嫁いだコジマが率いる、バイロイト音楽祭を担うワーグナー一族がある程度行います。

以後、ワーグナーの末裔としてバイロイト音楽祭は神格化されます
そして、当時のウィーンは、ワーグナー・ブルックナーの影響が強いです。その中から出てきたのが、この人たちでした。

ブラームス?あのカビの生えた音楽しか作れない間男?

ブルックナーみたいな作曲をしたいなあ
さらに、ワーグナーの一門入りしたことで、この人も躍り出ます。

昔はブラームスの方が好きだったけど、
ワーグナーを超えてみたいなあ
しかし、結局のところ、ワーグナーという個性がいなくなったことで、ふわっとワーグナー対ブラームスの対立は解消されます。結局、以後以下のようなワーグナーとブラームスのいいとこどりをした人たちが、ドイツ音楽の本流になっていきます。

ブラームスさんみたいな曲で、
ワーグナーっぽい癖をつけてみたらどうなるだろうか?

この路線の延長線に、
偉大なバッハやモーツァルトの楽曲を組み込んだら面白いことをができるかも?

今の新しいフランス音楽とかも混ぜてみたらどうなるだろう?
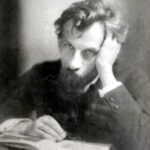
けしからん!
で、ロシアの音楽という見出しで、なんでこんな長々とドイツのことを書いたのかという理由は2つです。1つは、何度も言っている通り、ロシアの音楽はこの頃だいたいドイツからの輸入だったこと、もう1つは、ワーグナーという個性があまりにも強すぎて、受け入れるのに相当苦労したんだなあというのが読み取れることです。
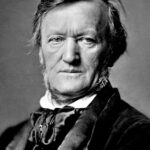
エンタメ!新機軸!革命!
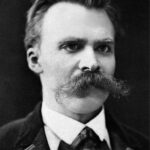
私も一時期ワーグナーなら世界を変えられると思っていました。
今ではもう昔の、忘れたい過去ですがね
そんなワーグナーですが、売れる前の1863年に一度ロシアに呼ばれています。その時、彼が今ではもう当たり前になっている客席に背を向けて指揮をしたことに、衝撃を受ける聴衆もいました。ですが、この人はこんな感じでした。
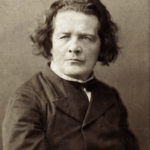
まあ、こんなもんか
一方、この人は若干トーンが違いました。

新しいことをやろうとしている。
取り上げる価値はあるかもしれない
この人が結構取り上げた結果、チャイコフスキーが結構コロコロ意見を変えます。

1863年のワーグナーの演奏を熱心に通ったけど
よくわからなかったよ……

オペラをちゃんと勉強したら、
あの頃ワーグナーがやっていた曲は素晴らしいものじゃないか!?

ドイツ音楽をちゃんと勉強したが、ワーグナーが今やってることは何なんだ!?
バイロイト音楽祭までいやいや行ったけど、聴きに行くんじゃなかったよ……

いろいろ悩んだけど、良くも悪くもワーグナーは偉大だと思うよ……
しかし、これは彼がチャイコフスキーだからで、別の立場である5人組の場合ですら、割れました。

ワーグナーのやり方は間違ってる!

あんな音楽に影響されるなんてけしからん!
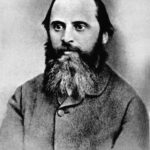
うーん、手放しでほめられんやつではあるが……

上の人たちがどう言おうと、
あれは素晴らしいと思う
で、これが例えばグラズノフだったり、タネーエフだったりといった、1880年世代になってくると、もうワーグナーの音楽性を自然なものと受け入れています。つまり、ワーグナーの音楽性はこのくらいの頃にロシアでもまず前提として共有されていくのです。

旧ソ連時代の伝記だと、なぜかアンチワーグナー扱いされていますがな
ということで、メトネルは世代的に生まれた頃にもうワーグナーを自然なものとしている作曲家が活躍している頃です。ということなので、メトネルにとって、理想の音楽側にワーグナーが含まれてることもごく自然なのです。
一方、1873年にエレーナが亡くなることに象徴されるように、パトロンの層が入れ替わります。つまり、これまでの皇族や貴族から、新しいパトロンが目立つようになります。
この時期を象徴するパトロンとして、ペテルブルクの木材商人ベリャーエフ、モスクワの鉄道王マーモントフの2人がいます。彼らのようなブルジョア資本家によって、音楽院出の作曲家が支えられる、というのが19世紀末のロシア音楽界、というわけです。

音楽院があるおかげで、
有望な若手を青田買いしやすくなったな

まあ、金がある人間が箔をつけるために援助するというのは、
いつの時代も変わらんのですよ
この有名な例こそ、チャイコフスキーの伝記に頻出の、鉄道業で成功したフォン・メックの未亡人こと、フォン・メック夫人です。

何かと必要でしょうから、
私が助けましょう

助かります
ベリャーエフは、リムスキー゠コルサコフ、リャードフ、グラズノフの3人を従え、このベリャーエフサークルが若手の登竜門として機能していました。
そして、上記のマーモントフの従姪こそが、スクリャービンの指導を受けた後、夫のモロゾフの遺産もあってモスクワでサロンの女主人として君臨し、メトネル兄弟ともかかわっていくマルガリータ・モロゾワだったりします。

いとこでもある彼女の父・キリルが没落して自殺したので、
後々親戚中で援助したのですな。
といってもそこそこ遠い親戚なので、そこまでエピソードもないのですが……

母方の援助もあり、当面の生活もしのげました。
少し経って父方のマーモントフ家の援助も受け、音楽などの芸術を学べるようになります
